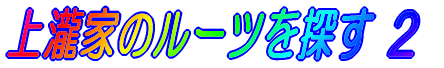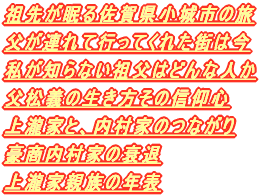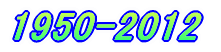| �@�@2025.1.�@���j���A���I�[�v�����܂����F���� �����C�ł��� ���d�b�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@musick�@(�J�[�y���^�[�Y)14 |
| �@�@�@�@�@2025����u�V�����̃��[�c��T���o�`�q�s�R�v���������� |

1981.5.�@���ꌧ����s�i�����ɂĕ��A��돼�`�A��A���V�G
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ē��l ��a�O�Y�ہ@(���E�N)�@




��y�^�@�Ƃ����M�ɔM�S�ȕ����A�c���̒n��K�₵�A�E�N�A�N�Y�ɐ�c�̒n���������苳���Ă�����������!!


���ꌧ����s�A�c�� ����Y�䂩��̒n�A�i������1980�N����ɖK�₵���Â��T�@�̎�������
���Ƃ̃��[�c��T��
���Ƃ́u���傤�����v�Ɠǂ݂܂��B�����Łu���v�Ə����Ă����l�Ȃ������Œʗp���܂��B
���̏��Ɛ�c�̑����͍��ꌧ����s�����a���A����s�ɂ܂�����L�����ɂ���A���{�����ł����������ɏW�����Ă���܂�����A���̒n������Ƃ̃��[�c���n�܂����Ǝv���܂��B
���̒n���玄�̑c���A����Y���k��B�s���q�ɂ���ė��Ď��B�̃��[�c��z���Ă��ꂽ�̂ŁA���R�s��������͍��ꌧ�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����30�˂ɂȂ������땃�A���`���u�E�N�ɂ���x�A��c������n�������Ă����Ȃ�����v�Ƃ������ƂŁA��̓N�Y�ƕ�̂S�l�őc���A����Y�����܂��������ꌧ����s���钬�̎��Q��ƁA���̏]�Z�ł����끛������Ƃɍs����������A���Ƃ̃��[�c�T�����n�܂邱�ƂɂȂ�܂��B


���a56�N�T���A���ƕ�A��̂S�l�ōŏ��̖K��n�ł���A�]�Z�̏�끛�������֍s���܂��B
���̕�����������̈ē�����H���܂ł����b�����A���͂��̉Ƃœ��܂��B
���Ȃ��F���������悤�ł����A���̕��̑��q���A���̗L���ȋ����I��A���a������ł��邱�Ƃ���Œm��܂��B
�������Ȃ���A���̎��͂܂������̑I��ł����B���̌�A���̒n��K��邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����āc�c




���Ƃ̂ӂ邳��
���B�Z�킪���܂������k��B�s���q�A�O�Y�ہB�{�Вn�͎O����̒n���ł����A�������̒n�Ŏ��Ƃ��N������Ƃ��ďZ�������˂��Ƃ��w�����Ă���n�܂�܂��B�@
���̑O�܂ł͎O���쏗�w����̑݉ƂɏZ�݁A�c����A�o�A���ƈꏏ�ɏZ��ł��������ł��B
���̐V�����ƂŎ��B�Z�킪���܂�炿�܂����A�Ȃɕ��A��ォ�畜���̎���ł������畃�A��͑�ς���J���ꂽ�悤�ł��B
���̒��ŕ����ĂT���̎O�Y�ۏ��w�Z�A20���قǂ̑������w�Z�ɒʂ����ƂɂȂ�܂����A���̍��̊X���͓c���{�������A�����c���₵�A���c�ɂ͎��R�̐��������E�W���E�W�������A�̂ǂ��ȕ��i������܂����B
����Ȋ��̒��Ŕ�ђ��˂����ォ��Љ�l�ƂȂ��Ă��������ł����A����̑�l�B���玄�B�Z��͐���������ꂽ�C�����܂��B
�n�R�Ȑ��������Ă�������]�v�ɐl�̏�𑽂������������Ǝv���܂��B
�c���A��뒷��Y�A���ꂿ���̂���
�������܂��O�ɖS���Ȃ������ŁA�J�l�����������ɂ́A�Ⴂ���듩�|�t�ł���A���t�Ƃ��ē��{�S���𗷂������Ƃ������܂����B
���̑c���̎��Ƃ́A��Œm�鍲�ꌧ����s�ł����A����Y����͎Ⴂ�����̒n������A�����āA�s�������悪�k��B�s���q�ł���A���̒n�œ����`�G����ƒm�荇���A�������ĕ������܂�A�J�l���������܂�܂����B�����a�C�����ŎႭ���ĖS���Ȃ�܂�����A����A������i���j���ꐶ�����w�͂��Ė���ė^�������ƁB���A�������w���̂��납��f�b�`����Ƃ������Ƃ������Ă��܂�����A�펞���͐�����J�����悤�ł��B
������ɂ��掄�B�A���Ƃ̃��[�c�͍��ꌧ����s�̋��Ñ��ɂ��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂��A���̂��Ƃ�ǂ��m��������܂���B�肪����͏��a56�N5���ɍs�����A���̕��̉ƁA�����Ă�����������܂���B���̏�ŁA����Y�������Ő��܂�āA���̕��A��A�e�ʁA�Z�킪�ǂ��Ȃ��Ă���̂��A���͒m�肽���̂ł��B
���A��돼�`�̒a������A���̐�����
�`�G���k�����̂����łU�l�̎q�������܂�A���̂T�Ԗڂ����A���`�ƂȂ�܂��B
�펞���ł�������A����Ŏq������Ă钆�ő�ςȋ�J���������悤�ł��B�ڂ����Ƃ���͓����Ƃ̃y�[�W�ŏЉ�Ă��܂��B
�`�G���������͏�뒷��Y����ƍč����A���A���`�����܂�܂��B���̖��̓J�l��������ŁA�v�c�Ƃɉł��܂��B
���̋`���̌Z�ƂȂ�����v�Y����A���L�N�G����A�����Ȃ݂�����A���ߎq����̂U�l�́A���ꂼ��̃y�[�W�ŏЉ�Ă���܂����A�U�l�̎q������Ă��`�G���������́A�����Ŋ��܂ŊŎ��A�������w�Z�R�N���̂Ƃ��S���Ȃ�܂����B
����ȗD�����������܂��������͔��Ɍ��������̂�����܂��B
�吳���珺�a�ɂ����Ă̎���́A�����O�̐���������A�푈���������A�������������q���B�ɂ��y���ł�����܂��B
�c�q���U�l��Ă�`�G���������́A���`��Ή��ɕ�������܂��B���̂Ƃ��̋�J�b�����Ƀ^�R���ł��邮�炢�����畷������܂����B����͖����T���ɋN���ĐΖ�������E��̑|���B�w�Z����A���Ă���R�̎G�p������A�������A�h���v���o�������������悤�ł��B
����ƁA������h�����Ƃ͉E�ڂ������Ȃ����Ƃł��B�c���Ƃ��a�C�Ŏ��������̂ł��B�ł��A���̂������ŕ����ɍs���Ȃ��Ă��̂ł����B
���̌�A���E�l�Ƃ��Ē�q���肵�A��l�O�ɂȂ�܂��B�S�������Ƃ��A���Y����͌Z���q�Œ��̗ǂ��������ł����B
������30�˂���ŕ�A���V�G�ƌ������������邱�ƂɂȂ�܂��B���̗��N�̂Q���A�������q��P�Ő��܂�邱�ƂɂȂ�܂��B���a25�N�̂��Ƃł��B
���̌�A�Ƃ��w��������A�̋@�B�����肵�āA�E�l���T�`�U�l���܂����̂ŁA���Ȃ�撣�����悤�ł��B�������Ȃ��獂�����ŋ�����Ă����̂ŁA�Ԃ����ꂸ�|�Y�ƂȂ�܂��B
�����ŕ���̋����h�Z����������A�Ƃ����͔����߂��Ă���܂����A���̍����i�X�Ǝ��c�Ƃ��J����肷��悤�ɂȂ�܂��B
 �@
�@
����ȂƂ��Ƃ̋߂��ɏ�y�^�@�̋������L�߂鎠�ꌧ��Îs���畧�t������ė��܂����B�����đ傫�ȉƂ����Ă܂��B���̕��t����̒��������Ă���܂����A�F�X�ȕ\��̒��������炢�A�d�����d�˂Ă�����A�������̕��t�Ɛe�����Ȃ�A��y�^�@�̋��������̓���Œ������ƂɂȂ�܂��B���R�A��⎄�B���ʂ��悤�ɂȂ�܂����B
10�N�قǂ��āA���̂����A���ꂪ�k���Ɉړ]���܂����A���̕Ӎ����畃�Ɠ���剺���Ƃ̂�������������A�i�X�Ɠ��ꂩ�牓�������Ă䂭�p�����܂����A����ł��������d�̑O�ł��o�������镃�����܂����B
��͔x���j�Ƃ����a�C�ŁA���̕ی���Ȃ�����A�މ@�̌J��Ԃ��ł��B
�������w�Z���璆�w�A���Z�܂ł��[���ƕ������c�Ƃ����Ȃ���Ǝ������A���B�Z�킪��������Ă��܂����B
���B�����������ĉƌv���ǂ��Ȃ�A����a�C������K���Ȑ��������炭����܂����B
������A�����Ȃɂ���m�q�������Љ�܂��ƁA�e���������悤�Ȏ����Ŋ��ȗm�q���������Ă��ꂽ���Ƃ�z���o���܂��B
���̌�A�]�[�ǂœ|�ꔼ�g�s���ɂȂ���@�B�V�N�ԕa���ʼn߂����A�m�q�������钆�����Ă��܂��܂����B
���̑��V�͍s���s�{�m�m�ɉƂ����Ă���A�N�Y�ƈꏏ�ɏZ�ޕ�̌��ő��������܂��B�ꂪ�C�ɓ����Ă��鐳�R�� �Z�E�̐��y���s����ɂ����炩�Ɉ���ɗl�̌��֍s����܂��B76�ł����B


���͏�̌|�p�ƁA��͂��O�����M��
������Ԏ������Ă������ƁA����͏�d���ł��B
���E�Ƃ����n���Ȏ�d���Ȃ�ł����A�̂���b���グ��ꂽ�Z�p�́A���̐E�l������Y�[�b�Ə��Łu���`����̎d���͋C�������������đf���炵���v�ƕ]���̏��E�l����ł����B�������A��P���d�グ��H���Ɏ��Ԃ������A�O����ɂ��Ă��P��������H�ƁA�Ȃ�ƁA���ł����łȂ��Ă��l�i�͂����ς��܂���B�ǂ��d������������ƌ����āA�����������鏤���łȂ������ׁA�e���͂��������肵�Ă��܂����B�u�����Ő��^�ʖڂȐ��i�͏����l�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�����ꂪ�����Ă���܂������A�Ƃ��Ƃ��Ō�܂ł��̎d���𑱂��܂����B
����Ȑe���̐��i�����炢�����w�����Ă���܂����A���̐��^�ʖڂ��ƈ�̂��Ƃ���萋����K���o���͐������̂�����܂��B
�e���̎�ł���A���b��ƂȂ����͈̂���ɗl��M����M�ł����B�S�O�˂̍�����n�߂��O���ɁA���������邮�炢�̈ӋC���݂��������͎̂������ł͂���܂���B
���ƔӁA���o�������镃�̐��͂��������͂�����܂��B���̕ӂ̂�������̂��o���Y�[�b�Ɨ͋����A�O���̈ꌾ�X�X�ɋC��������A�����Ă��镃�Ɂu�����ɂƂ����Ă���v����ȋC�������܂����B
�������A���o���グ�Ă���Ƃ��Ƃ͑ΏۓI�ɁA�H���̂Ƃ��͗D�����ɖ������Ă���A�����A���ӁA�q���B�ɕ��l�̂�����������̂ł��ˁB�����A�E���U�����邮�炢�ŁA�����������Ă��܂��ǁA���͈���{��܂���B
�L���Ȑ������ł��Ȃ������̂͑S�ĕ��ɐӔC�����镪���ł͂���܂���B�ꐶ���������Ă�������̒��ŁA���ɐ��̒����Ă䂭�u�m�b�v���Ȃ���������A�����z���܂��B


���A���`�����ꂽ��Ȃ���
�u�q���͕�A�q���̍K���͐e�̍K���ł���v�ƕ��͌����܂��B
���Ƃ̉�b�̒��ł́A�K�����l�̂��b���������Ă��܂��B�l��M����Ƃ��A���̓��Ƃ��A�M�̗͂Ƃ��A���߉ޗl��O���A�����̈̂����V����̘b���A�F�X�B���ꓙ�͑S�ĕ����M�����Ă��铹��(����)�Œ����Ă������Ƃ������Ă���̂ł��B�̂��搶�̂��b�����q���ɕ������邱�ƂŁA�������g�̕������Ă����̂����m��܂���B
���̐S��D���������Ă���ƁA���̐l�����ǂ�������܂��B
�������������̂͂�������܂����A�q��������Ȃ��A�����Ďq��������Ȃ��l�ł����B�l����D����A�����̐l���䂪�Ƃɏo���肵�܂��B���̐l�Ԑ��́A�D�����Ƃ��l�D���A�����ĕ��l��M��������̖����S�ł����B���ꂪ�䂦�ɐ����������܂������A���̕��A���B�q�����͋���������Ƒz���܂��B
�ӔN�͔]�[�ǂŔ��g�s���ɂȂ�A�V�N�ԓ��@���������܂����B�ꂪ�����̂悤�Ɋŕa�ɍs���܂�������ǁA���B�͂���ɊÂ��ĂقƂ�ǂ��Ă�邱�Ƃ�����܂���B�₵���^���ł��������Ƃ��Âт܂��B
��돼�`�A�����@�ߋ`�~�A����10�N12��14���@�S



��A��냈�V�G�̂���
��̐��܂��������́A�����Ƃ̃T�C�g�ŏЉ�Ă���܂����A���A���`�ƌ������āA���炭�͍K���ł������Ƒz���܂��B�������A��ォ�畜���̎���Ő��̒��݂�ȕn�R�ł����B
����Ȓ��A��������̕��͏��E�Ƃ��Ď��Ƃ��N�����܂��B���R����ꏏ�ɂȂ��āA�����������x���܂Ŏd���ɐ����o���܂��B����̓C�O�T�������d�ɂ��d�ˍ��킹�Č����W�p�قǂ̏������܂����A���̍�Ƃ���ςȂ�ł��B
����ꐶ�������̉��������܂��B
�����o������E�l���\�C�O�T��A�w���Ƃ������n�ŗ��[�𗯂߂āA��ꖇ������Əo���܂��B�����A���̏�̏d�������Ƃł��B����ȏd�J��������A��͕a�C�ɂȂ�܂��B�x���j�Ƃ����āA�������w�Z��w�N����W�N�ԁA���މ@�̌J��Ԃ��ł����B��������Ǝ������Ȃ���q���B�̐��b�����Ă���܂����B������C������Ƃ��́A�g�E�t������̃o�C�g��F�X�ȃA���o�C�g�����ĉƌv�������܂��B���̂��Ƃ��q���ł��鎄�B�O�Z��͂Ԃ��Ɍ��Ă��܂����B
����ȕ�̎�͗x��ł����B�Ă̖~�x�肪���������ŁA��������̃N���u�ɂ��Q�����āA�V�l��̈Ԗ₩��w�Z�A�o�s�`���̍s���Q�������Ă��܂����B
�����Ď��B�q������l�ɂȂ�Љ�ɏo��ƁA����ƕ�炵���y�ɂȂ�A��̕a�C���قڊ�������A�k��B�s�⏬�q�̊X�̐F�X�ȃC�x���g�s���̗x��ɂ͕K���ꂪ���܂����B
����ȂƂ������]�[�ǂœ|��A���@���܂��B�V�N�Ԃ̕a�@�ʂ�������܂�������ǁA�a�C��������C�ȕꂪ��Ƌ��ɍs���s�Ɉ��z���A�����ł��u�p�v�Ƃ����x��̉�ɓ���A��������Z��A�s���s���̍Ղ肩��A�N�Ɉ�x�̍s���s����قʼnp�̔��\�����܂��āA���������[�������y�����ꐶ���I�����Ƒz���Ă���܂��B
��̐������́A�F�𑽂���邱�Ƃ����ŁA�������^�������ɐ����A�g�̂������t�̒��ŁA���̏d����`���Ȃ���F�ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃ����ł������Ƒz���܂��B
�s���s�{�m�m�Ɉ��z���ĂW�N�]��A����̐��R������Ɩ��ڂȂ��t������p�ɂɂ��Ȃ���A���{�̂����������A�R�c�̂��������A�p�搶�⒬����A�V�l��A��������̐l�X���爤����A���B�Ƒ�������钆�A�D�����Ί�ŋ����Ă�����܂����B
���悵���A�����@�@�@80�A����17�N�V��12���@�S


�����`�G�i�c��j�ƁA�����Ƃ̂��b��
�����X�˂̂���S���Ȃ����`�G���������́A���i���j������āA����Ƃ��ĕЖ�̏�y�^�@ ���~����ɗǂ����������ɍs���������ł��B
�@�b�����Ă���镧�t�̒��ŁA�����E�N����Ƃ������V����D���ŁA���̂��V����̖����ėE�N�Ɩ��t����ꂽ�Ɛe�����牽�x����������܂��B
�����`�G���������́A�R�����哇�S�哇���̓����ƁA�����Ƃ��Đ��܂�܂����A�����̃N���A�O���̃J�l�̎O�o���ł��������߁A�����`�G��18�˂̂Ƃ����{�q�����炤���ƂɂȂ�܂��B
�ڂ����������܂��ƁA�����Ƃ͑�X�̏�������ŕĖ≮�����Ă��܂����B
��������͕Ă�ݖ��A���A�Е��܂ŕ��L���c�ݍ����ł��������Ƃ��܂��B
���̓����Ƃɖ��{�q�ɗ���v������Ƃ͑D�≮�B���Ō����ݕ��D���R�`�S�n�C�����A�L�����������Ă����f�Տ��ŁA���̎��j���O�j�H�̋v������ƌ������܂��B�����ĂS�l�̎q�������܂�܂����B
�@�����̃L�N�G������́A���Ε��Y�i���q�k��j�ɉł��܂��B
�A���j�̋v�Y����͓����Ƃ��p�����ƂɂȂ�܂��B�i���q�k��O�Y�ہj
�B�����́A�Ȃ݂�����͖�����V������i��������j�ɉł��܂��B
�C�O�����ߎq�����
�ǂ����Ėk��B�s�ɂ���ė�����������܂��A���̋v������͎q���B��u������ɂ��āA�ǂ����̊X�ōč������ƕ����܂��B�i�v�c�J�l��������̘b�j
���̌�A�������ď�뒷��Y�i���̎��̑c���j�Ɠ����`�G���������܂��B�i�č��j
�D�����Ď��̕��A��돼�`�����܂�܂��B
�E���ɃJ�l�������܂�A��ɉv�c ������ɉł��܂��B
�Â��ːЂɂ͎R�����哇�S�哇�i���˓��C�̎��h�哇�j�����X�p���������Ƃ̒����A�����`�G�Ƃ��Đ��܂�A���a34�N�A���q�O�Y�ۂ�82�˂̐��U������̂ł��B
�������N���i�`�G�c��̖��Ŏ����j����̂��Ƃ͕�����܂���B
�������J�l�i�`�G�c��̖��ŎO���j����́A�k��B�s���q�ŗ� ���g����ƌ������܂��B�щƂ͑�X�p����邱�̒n�̖��Ƃł��B�ޖؖ≮�����Ă���܂������Ƃ�����A�J�l������͍K���ɕ�炵�Ă����ƕ����Ă���܂��B
�k��B�s�̓����Ƃ͐₦��
�����m������Ƃ̌�p�҂͂��܂���B�����������玟���̓����N������̂���c�����h�哇�œ����Ƃ��p���ł��邩��������܂���B�J�l�������b���ɂ́A�R�����哇�̕Ė≮���A�L�����������Ă��������Ƒc���́A��������̏ؕ��ݕt����S�Ĕj�����A�����̐l�X�ɂقǂ�����!!
�����ł��B�����ƁA���Ƃ̐l�X������ƕ����肻���ȋC�����܂��B
���q�A�����Ƃ̂���͏��q�k�恛�����ɂ���܂����A�����m��Ȃ������ƌÂ��ߋ������肻���ł��B���̗��j��m��ɂ́A�܂��܂����Ԃ�������܂��B
�����`�G�i�c��j���k�����̎q���B
�@�����̓����L�N�G����́A�k��B�s���q�O�Y�ۂŔ��Ε��Y����Ƃ����R�l����ƌ������܂��B
�T�l�̎q�����ł��A���j�̔��Ε�������Ǝ��͋`���̏]�Z��ɂȂ���ł����C�ł��߂����ł��B
���������ł���ׁA�q���̍��̎��͐����L�N�G�����������ꂽ���̂ł��B
�A���j�̓����v�Y���{���A�����Ƃ��p�����ƂɂȂ�܂����A��������ĊԂ��Ȃ������܂��S���Ȃ��A���O�����{�q�ɂ���܂��B���O����͏]�Z��ɂ�����܂����A���������ł�����܂����B
��������ď��̎q���O�l�ł��܂������A���O�������S���Ȃ��A�����܁A�q������Ƃ����Ƃ̍���ɋA���A�������r�₦�܂����B
�B�����̓����i�~�G����́A�k��B�s��������̖�����V������ƌ�������A����Y����Ɩ�����ł��遛�������܂�܂����A���̕����S���{�~�X���j�o�[�X�̋�B��\�ɑI�ꂽ��ϊ��ȕ��Ɛe�����������Ă��܂������A�Ⴍ���ĖS���Ȃ��������ł��B
�C�O���̓������ߎq����ɂ��Ă͕�����܂��A�߂��e�ʋɗL������̖�������܂�����A������̕��Ǝv���Ă���܂��B
�D�v������ƌ������������`�G�i�c��j����ɂ́A��̂S�l�̎q�������܂������A������A�v�����Ƃ��o�Ă��܂��܂��B���̌�A��뒷��Y����ƒm�荇���A�č����邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ď��̕��A��돼�`�����܂�܂��B
�E��N�قǂ��ď��J�l�������܂�܂��B�J�l������͏��q�������ɋ߂Ă������A���������Ă����v�c ������ƒm�荇���������܂����A������͉v�c�Ƃ̃T�C�g�ŏЉ�Ă��܂��B
�F�O�v�̓����v������A�č�������뒷��Y����Ƃ̊ԂɂU�l�̎q������Ă��`�G���������́A��ϋ�J����܂������A�ӔN�A���̎���N�Y��A��Ă����Q���ǂ��������Ƃ��܂��B���ŗD�������������ł����B
�����ƁA���ƂɊւ�邨�b��
�����ł̂��b���͕��A��͂�����̋L���Ɣ��Ε�������A�v�c�J�l�������瑽�����������Ƃ��L�ڂ��Ă��܂��B
���q�k��O�Y�ۂ̏�돼�`�Ƃ̎���ɂ͑����̐e�ʂ����܂��B�݂�Ȍ��̌q����̂��������ł������A�e���̕��A�ƁA�D�����A�l�̗ǂ������ڂɂłāA���̒n�����邱�ƂɂȂ�܂������A���ɂƂ��Ă͌̋��ł��B���A�O�Y�ۂ͓s�s�̈�ƂȂ�A�����̐e�ʉ��҂����̒n��蕪�U���܂����B�₵���Ȃ�܂��������܂��̒n��K��A�̂�z���o�����Ƃ�����܂��B
�́A�����v�Y���������ӂ̂悤�ɕ��C�ɓ���ɗ��܂��B�E�N�A�N�Y�A����Ɖ������Ă���A�ǂ���������������܂����B�u���V�������̂��Ƃ𗊂ރ]!!
�v�ƌ����ċ����Ă��܂��܂������A�����̂�������̌���p���������܂���B
���L�N�G������������܂��B���`����ɂ͎O�l�̒j�̎q������u�q���͕�W���[�v�ƌ����āA�n�R���܂��Ă��ꂽ���Ƃ�x�X�q���Ȃ��畷���܂��B���̑吺��グ�邨����́A�������B�ɂ�������������A�D�������Ă���܂����B����������^�ʖڂŁA�e���ɂ��Ă������Ƃ��Z�o���F�߂��؋��ł�����܂��B
�����v�Y���������Ȃ̂悤�Ɍ����Ă��܂����B�u���ʑO�Ɉ�x�A�哇�ɍs���Ă݂���!! �v�ƁB
���̌��C�ȂƂ��A��čs���Ă��悩�����A�Ɖ���܂�܂��B
���̋C�������A�����Z��Ŏ��h�哇�ɍs���A������������Ȃ������Ƒc��̂���Q����������A��������̍D���������u�I�܂イ�v�������āB
���̎����b��
�������C�ł�������A�d�����I���A�[�H�̂�����Ƃ̎��������ȂނƂ��A�I���͏��Ƀ��e��!! �Ƃ��A���Ƃ݂͂�Ȓj�Ԃ�Ƃ��A���l����ł������Ƃ��B����ŗE�N�ƓN�Y�͕�Ɏ��āA���삪�����I���Ɏ��Ă���Ƃ��A�F�X�B
���l����Ə��Ƃ̐l�X�݂͂�Ȏl�p��Ŗڂ���d�B����ɁA�݂�Ȑ����傫���B���������ƂȂ������i�ŗD���������B����ȕ����A�����Ƒ�ɂ����������B
�������̃T�C�g�����āu�����Ƃ̂��Ƃ������Ă�����������v������܂����琥�d�b�������B�����炩��f���܂��B��.fax�O�X�R�O�|�Q�S�|�O�P�X�X�ł��B
��낵�����肢���܂��B
���Ƃ����@2008.1.1.
�l���͒����ĒZ�����̂ł��B�u���A��̂��Ƃ��v�Ƃ́A�Ƃ��̗���̑����������܂����A�����c��킸���ł��B���̒��ō��A�����ł��鎖�́A����c�l���h���S�ł��B���Ƃ̃��[�c�A�c��Ƃ���Ɍq����e�ʊW���������Ɛ������A���̎Ⴂ����ɂ��̑��Ղ��c���Ă��������̂ł��B
���̏�ł�����ӂ̐S�ł���c�l�Ɋ��ӂ��A���������čK���ł��邱�Ƃ��F��A���̐��ɐi�߂�ꂽ��̊肢�ł��B


���Ƃ̃��[�c��T��
���ꌧ����s�A��뒷��Y�A��c��T����
�����Z��ł���s���s�ɂ͏��Ƃ������̕��w�ǂ��܂���B�m�s�s�̓d�b���ɋL�ڂ���Ă���̂͒�Ƒ��ɂQ�������Ȃ�ł��B���̂����ꌏ�̕��́A���ꌧ�o�g�ƕ����Ă��܂��B
�ȑO�Z��ł����k��B�s100���l�̒��ł��A���Ƃ������O�̕��͓d�b�������ł��A�ق�̐����������܂���B���ꂮ�炢���������O�Ȃ̂ł��B
�������A����c���܂��W�܂鍲�ꌧ�ɓ���ƁA����s�������Ő��S���B��a���⏬��s�ɂȂ�Ɛ����������܂�����A�������O�̂��X��L���A�Ŕ�����Ƃ�����ƈ��S���܂��B���̂悤�ȍ��ꌧ�ɂ����뒷��Y�����������̃��[�c��T�����Ƃɂ��܂����B
�����������a�T6�N�T���ɕ��ƕ�ɘA����ĖK�₵���e�ʉƂƁA�����ɍs���Ηǂ����ƂȂ̂ł����A���̌�A�S�����t�����Ȃ��B���̎����Ƃ��莆�A�A���������܂���A���č���܂����B
����Ŏ��̋L�������ōs���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B
����18�N2���̓��j���ł��B
�������A�m�q�����̈��ԁA�z���_���C�t�̓c�^�G�ꂳ�����Ă��ꂽ�s�J�s�J�̐V�Ԃł��B�J�[�i�r�����邵�A�e���r�����邩�烋�������C���ŁA��B�����璹��
�h �b�ʼn��Ԃ��A�����R�S���������ɍs���A�i�q��O�R���w�������āA������ӂ̐l�Ƃ��^�N�V�[�̉^�����ɕ������番����Ǝv���Ă��܂����B
������Ǝ��Ԃ������āA�̂�т荑���R�S�����ƕ��s�ɑ���d�ԓ��ɔ�O�R���w�������A�������炿����ƎR��̏�ɂ���������͂��A�ƁA�v���Ă��܂�������A�����Ȃ肨���T���ł��B
�P���A�Q���c�c�T���A10�����炢�����������ẮA���Ȃ̋L���Əd�ˍ��킵����A���̂����ɓ����āA������ƕ������肵�܂������Ǖ�����܂���B
�Ƃɂ����A�����̕�n�ɂ�����̂����T�����ƂȂ�ł���ˁB��������̂�����A�������Ⴂ�܂��B�Z�E�ɕ����q���g�����炢�A�Ăѕ�������̂����ɍs���B�������āA���̂����ցB
���ꌧ�ɂ͂�������̂���������A��y�^�@�ł����A���A��J�h�Ƃ��A�T�@�A�ՍϏ@�ȂǐF�X�����āA���������荬���肨���̏@�h���ĕ��G�Ȃ�ł���ˁB�����ŁA�Ƃ��Ƃ����̓��͒��߂ċA��܂����B


���Ƃ̒T�K�Ƌ������{�Ƃ�K�˂�
����17�N�V���A��A��냈�V�G���S���Ȃ��Ď��̔N���� ������i��̒�j������A�������{�Ƃɕ����A�܂����̍��T���Ă��܂��B���Ƃ��ẮA�قƂ�lj��̂Ȃ��{�Ƌł����ǁA��̏]�Z�킪�������������ɋ������{�Ƌł�����A���R�A������͂����瑤�Ƃ̂��t����������̂ł��傤���A
�����ŕ�̎O������I������A����̋����ƂɖK�₷�邱�Ƃɂ��܂��B
�������������Ă��ꂽ�Z�������ł����A�֗��ȃJ�[�i�r�ŒT���čs���܂��B�����ČZ��̕��Ɩʉ�ł��āA�܂�������������ē����Ă��炢�܂��B
30���N�O�A��ƈꏏ�ɍs�����Ƃ��́A���̑傫�ȋL�O��̂悤�ȕ�͖����Ȃ��Ă��܂������A�V�����u��������ꂽ�傫�Ȃ���ɂ����A���A�������ɂ��鋍������c���܂̔[�������͂��߁A�����܂ɂ����A���ď�������̂��̂�u���Ă��܂����B
�����āA���{�ƂƂȂ���傫�Ȃ��Ƃɍs���܂��ƁA�������S�n�ǂ������܂̈ē��ŁA����c���܂̕��Ԃɒʂ���A�m�q�����ƈꏏ�Ɏ�����킹�A����܂ł̂��t�������Ȃ��������Ƃ̂�����ƁA�c��
�h�Z�����������̂��ƂȂǁA���b�����Ă��炢�܂����B���A�A�肬��Ɏ���̃I�~���Q�܂Œ����āA�����[�����ӂ��邱�Ƃ���ł��ʂ�����܂����B���̌�A�O�x�قǂ��̒n��K��A�����ɁA���Q�肵�Ă��܂��B
�O�x�ڂ̍���A���Ƃ̒T�K
����20�N9���̓��j���B
���̂悤�ȕ���̍���s�A�����ƂƗׂ荇�킹�̏���s�̏��Ƃ͉����̏����킹������̂ł��傤���H�A�܂��A��뒷���Y�����������̂���c���ܒn��T�����ĂĂ��܂���A����ō��x�͎O�x�ڂƂȂ�܂��B���̂Ƃ��͒�ƎO�l�ōs�����Ƃɂ��܂����B
��͐́A���A��ƈꏏ�ɍs�������Ƃ�����̂ŁA�ނ��ڂ������Ƃ͒m���Ă������ł��܂��B����ŗm�q�����ƓN������l���A�v���E�X�̃J�[�i�r����������܂킵�āA�������A�������A��������T���B����s����O��Ē��茧�܂œ����Ă��܂����Ƃ�����܂������A���ǂ��̓������̂�������͌�����܂���ł����B


�����Q1�N2��22��(��)�܂̂��J�A���ꌧ���ÁA�i����
������J�A���X�������������ăC���Ȃ��V�C�ł����A�m�q�����̃z���_���C�t�ŏo�����܂��B���̎Ԃ́A�m�q�����̂��ꂳ�����Ă��ꂽ�V�ԂŁA�ی�����J�[�i�r���������S�Ă�t���Ă�����Ă��܂��B
����ȃi�r�ɍ���i�q���Éw�ɃZ�b�g���ďo���͌ߑO�W���O�B
�����̂悤�Ƀz�b�g�R�[�q�[���َq�����������Q���Ă��܂��B�r���A�É�r�`�ł��y�Y���T���w�����āA�������̎��̏��������Ă����܂��B
 �@
�@
�����a�h�b�ō~��āA�����R�S���A���Éw��Ԃɂ����ނ��i�������Љ�Ă��炢�܂��B����Ǝ��̏Z���^�ɂ��i�����̂�������̖�������܂��B����͎O�N�O�A�K�₵���Ƃ����Éw�O�̎ʐ^�ق���ŁA��뒷��Y�ʐ^�̗��ɏ����Ă���Â��Z�����ː�ŁA�ߕӂ̏�y���̂����̏Љ�i�����������̂ł��B���̂Ƃ��K�₵���Ƃ��͗���ŁA����͂��܂茩�ĂȂ������̂ł��B����ɂ��̂����A���N�O�ɂ��������Ƃ�����܂�����A�����Ŏl�x�ځB������������ܓx�ڂ̐����ɂȂ邩���m��܂���B
 �@
�@ �@
�@
����34�����ɐV�����o�C�p�X���o�������̉i��������͗Ր��@�̂����ł��B
�L���~�n�ɏ����ȏ��R������܂��B���̎R�̎Ζʂɂ��邨��̂Ȃ��ɏ��Ƃ̕悪����܂��B�L���̒��̃C���[�W�ŁA�����ƁA������d�ˍ��킹�Ă݂܂����A�܂�������܂���B��Ȃ̂̓C�O�T�����̂����ɁA���ʂɐ̖和������сA���̉��ɉƖ傪���邱�ƂȂ�ł��B�Â��ʐ^�����Ȃ���E���E�����Ă���m�q����A���̂����ɊԈႢ�Ȃ��ƌ����܂��B
�����ĉJ�̒��A�����ȏ��R�ɓo����30���N�܂���z���o���܂��B�C���[�W�ƈႤ���ŁA���Ƃ̕���O�A�l�m�F���āA�����̌��փu�U�[�������܂��ƁA�m�q�����Ɠ����N���̖V�炳��ɂ����A���A���Ƃ̐���s���̘b���ɁA�茳�̎ʐ^�����Ă��������āA�͂�����m�F�����Ē����܂����B
�u���Ⴒ�����܂���B20���N�O�A�����S�Ă����đւ��A��n�����Đ����ς��܂����v�ƕ����܂��B
�����̗��ɍ������o���āA���ւ����ɕς���������ł��B

 �@
�@
�����āA�V�炳�����̖{�����ē����Ă��������܂��B�����̂��߉ޗl�A���E�̂���ܑ�g���܁A�ω����ܓ������������������A���̉��Ŏ�����킹�܂��B�����ĕʊقɈē�����āA��Z�E�Ƃ�������Ȃ��b�����A�����������ɂ��َq���āA�z�b�g�ȋC���ŗǂ������A�ǂ������B�c��̐e�ʉ��҂��A���̒n�ɂ������邱�Ƃ�m���āA�������ӁB
����A������x�A�s�����قƂ����O�����͂����āA���ꂩ�����낵�����肢���܂��Ƃ��āA���d�b���܂����B





���ꌧ�_��A�����Ɛ�c������Q������22�N2��22��
���ƕ�̐�c���A�킸��50�q���ꂽ�Ƃ���ɂ��邱�ƂŁA���N�A��̂����������̐�c�����鎛�ɂ��Q�肵�܂��B
��������T�@���̂����ł����A�V�炳�����ɂ��s�݂ł����̂ŁA����Q��������Ă��������āA���ߏ��ɏZ�ގ��Ƃɂ����鋍���ƂƁA���̌Z��e�ʉƂɍs���A�ȒP�Ȃ����A���������܂��B
�J�̒��킴�킴�Ƃ������Ƃł������A���̂悤�ȐG�ꍇ���������Ƃ����������A���������A���A������ł����ł��傤�B
���A�ꂪ�o���Ȃ��������Ƃ����B�����ďグ���邱�ƁA�����Ă��̂悤�Ȃ��t�����̎d�����k��B�s�A�s���s�̏��Ƃƍ���Ƃ̌q������A�q���B�A�e�ʕ����A�[���q���Ă���邱�Ƃ�����āA�܂��܂����B�̓K���o���܂��A�Ƃ��Ă����܂��傤�B



�����Q2�N8���~�A���A���`�����A�J�l���f��������i���������Q��
��뒷��Y���ꂿ���̎q�A�J�l��������Ə��`����������ɂ��āA����A���Ƃ��{�Ƃ̂���Q������邱�ƂɂȂ�܂����B
����90�˂ɂȂ�J�l��������́A�܂���l�Ŕ������ɂ��s���邮�炢���C������܂����ǁA�����t���Y���Ă��鏟�`����i���j�j�Ɠ�l��炵�Ȃ�ł��ˁB����ŔN�ɐ��x�A���f�����Ă��b��������A���ԂɎ�����킹�Ă��t�������Ă��܂��B����ȂƂ��A��뒷��Y�����������̎ʐ^���܂����̂ŁA���̌��ō���̏��Ƃ̂���Q��ƁA�����Q������Ă��炤����ł��ē������܂����B
�W���̖~�x�݂𗘗p���āA�z���_�X�e�b�v�o���ŁA���������S�^�]���āA�킸���R���Ԃقǂʼni�����ɓ������܂��B
������Ă̂���Q��ł����A�����[�����������ł��B�u�E����A�m�q�����!! �v�ƌ��Ȃ̂悤�ɗ_�߂Ă���邨����ɁA�i�����Z�E�A�V�炳��Ƃ�����育���A���āA����̌������߂āA���X�̃I�~���Q�����Q���܂��B���`���A�������������悤�Ȃ����u��Y���āA����ɗl�A���߉ޗl�Ɏ�����킹�܂��B
�����͂��~�Ƃ������ƂŁA��������̂��Q��̕������܂������A���ʈ����ł����ĂȂ��������B�B
�k��B�s������ƁA�����āA���ꂩ��̂��t���������܂߂Čq���邲��c���܂̒n�B���̂悤�ȉ��������̒n�ɗ��āA�J�l��������͑喞�����Ă��܂��B����Y�����܂ꂽ�n�ł���A������̌̋��ł����邩��ł��B





2012.1.���Ƃ̃��[�c��T���A�܂Ƃ�
�Ō�܂œǂ�ł���āA��ς��肪�Ƃ��������܂��B
���B�l�Ԃ́A���ꂼ��̃��[�c��˂��l�߂܂��ƁA�������ɂȂ�܂��B
�l�ނ݂͂ȌZ��!!�@�Ȃ�ł��傤���A����ς��A���ꂼ��̂���c���܂���������m�肽�������ł��B
���Ɏ��B�̂悤�ȁA����ӂꂽ�Ƒ��ɂ͗]�v�ɒm�肽���B������Ƙ����Ȃ̂����m��܂��A���̂��Ƃ�Nj����Ă䂭�V�ѐS�Ƃ������A�ʔ���������܂��B���̏�ŁA���̂��Ƃ�e�ʁA�Z�킪���ꂼ��ɂ�������q�����Ă���āA���F�B�������āA�Ȃɂ����̌𗬂���������A�����ƍK���ɂȂ��A�����z���ď��Ƃ̃��[�c�T�������Ă��܂��B
�����Đ́A�����b�ɂȂ����A���e�ʂ̊F����ɂ��A�����̌`�ł�����������B����̑O�Ŏ�����킹�邾���ł����A����ł������̐S�Ŋ��ӂ̋C������`�������̂ł��B
�����ꎄ���A�݂Ȃ���̂Ƃ���ɍs���܂����A���ƍȂ��A�Z�킪�A�c���邱�Ƃ��A���̎Ⴂ����Ɏp����Ă䂯����A�����ƍK���ɂȂ��A����ȁA�܂�ʎ����y����ł��܂��B
�����ǂ�������A���莆�����̌𗬂ł���������K�ł��B
��낵�����肢���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012.4.10.�@���E�N�A�m�q






 �@
�@
2010.8.13.�@�~�@�������s���s�{�̓m�@���Ɓi���N�Y�j�@�O�Z��Ƒ��ŁA����c���܁A����ɕ��@���i�얳����ɕ��j�ց@��y�^�@�{�莛�h�A���R���A���y���s���܂̂��o�����������܂����B
 �@
�@ �@
�@ �@
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�[�g�t�H���I �s�n�o��
2017����u�V���������[�c���T���o�`�q�s�R�v���������� |